- 現在主婦(主夫)である
- Web制作会社に就職したい
- Web制作会社に就職するまでのプロセスが知りたい
こんな方に向けて。
僕は現在33歳の1児の父です。かつては地方公務員として7年働いていたが、3年前に退職して主夫(主婦)になった。
その後、独学でWeb制作スキルを身に着け、2023年12月にWeb制作会社から内定をいただくことができた。
有り難いことにWeb制作会社から内定を頂けたので就職活動を終了します。スキルはともかく、役所を退職した経緯、私自身の考えや価値観を評価いただいたことが大変嬉しかったです。自分一人の力では就職できなかったので、何よりもすぐそばで支えてくれた妻に感謝したいです。関わったすべての方にも。
— つる │ Web制作・コーディング (@Tsuruoka_1103) December 16, 2023
実務未経験のアラサー男が家事・育児をする傍ら、Web制作会社から内定をもらった就職活動の軌跡を赤裸々に綴っていく。※もちろん僕個人の背景や能力もあるので、すべての人に当てはまるわけではない
アラサー未経験でもWeb系の企業に転職したい!と志す方の参考になれば嬉しい。
また、1万字を超える長文になってしまったので時間があるときにゆっくり読んでほしい。
なお、とくにこんな方をイメージして記事を書いた。
- 30代である
- Web制作の実務経験はない
- Web制作の学習を始めている
- フロントエンドエンジニア、コーダー職を希望している
【正直な感想】現実は厳しいかも。

いきなりで恐縮だが、「アラサー未経験子持ちでの就職はかなり厳しいかも。」というのが第一感だ。
詳しく理由を説明する前に、僕のライフスタイルを知らないとあまり参考にならないと思うので、まずは僕のライフスタイルご紹介する。
ライフスタイルについて
- 夫婦+1児の子どもと暮らす
- 子どもは幼稚園に通っている
- 日中2〜6時間ほど自由時間がある
- お互いの両親のバックアップが受けられる
- 首都圏の郊外に住んでいる
こんな感じ。
一言で言えば、「都心まで電車で90分くらいの郊外に住む、1児のアラサー父」です。その昔は地方公務員をしていたが、育児に専念するために退職した。
学習スタイルについて
僕は子どもを幼稚園に送り出した後の時間を学習に当てていた。1日に慣らすと2〜5時間くらい。もっとデキる人もいるかもしれないが、私は2〜5時間くらいがライフスタイルに合っていた。
また、子どもの用事があればそちらを優先しました。休日は学習しなかった。
もちろん、人によっては早朝や深夜に学習できるかもしれない。しかし、私は日中の時間以外に活動することが苦手(受験勉強で悟った)なので、やめた。
また、育児や家事は子どもが帰ってきたら細切れにやってくるものだ。だから、子どもが家にいるときは育児と家事に専念していた。細切れの集中ではスキルは身につかないと考えたからである。
求人応募結果について【大半で不合格】
そんな生活を過ごすこと約2年。求人応募結果は以下だった。
応募総数39社のうち、面接は3社、最終的に内定は1社
応募の9割は書類選考落ちだ。不合格の連絡が来るたびに落胆していたが、不合格の連絡すら来ないこともザラにあった…。
| 応募 | 書類選考応募 | 書類選考通過 (面接へ) | 内定 |
| 企業HPから応募 | 39社 | 4社(1社は辞退) | 1社 |
理想と現実のギャップ
未経験アラサーからの内定獲得はかなり厳しいと思う。しかし、これが現実なのかなという気もする。
なぜか。
企業の思惑:最小のコストで、最大の成果を
一言で言えばこれが理由だ。経済合理的に考えれば、企業はなるべくお金をかけず、なるべく長く働いてもらい、そんでいて従業員にはなるべく多くの成果を出してもらいたい。これが本音のはず。
すると、まだ何にも染まっていない若者を低賃金で採用し育成したいと考えるはずだ。
もしもあなたが経営者なら、どちらの人を採用したいですか?
- 20代の独身で子なし
- 30代の既婚で子持ち
2人の能力は同じと仮定します。よほどの理由がない限り「20代の独身、子なし」を採用したいと思うはず。
「30代・既婚・子持ち」は子どもの送迎で長く働けないかもしれません。頻繁に子どもの病気対応で休むかもしれません。低い給料に納得せず、文句を言ってくるかもしれません。年齢的に新たなスキルを身につける能力が劣化しているかもしれません。
でも、20代の独身子なしならその心配は無用だ。資本の論理に従う限り、20代の独身を採用するのが合理的になる。ドライで冷たい話だ。
「いくらなんでも冷たすぎる…」と思ったかもしれないが、これは社会システムとしてそうなっているのであって、個人で抗うのは難しい。
では、どうするか。後ほど詳しく話す。
未経験就職の現実を知っていただいたところで、就職するまでの道のりをご紹介したいと思う。
就職活動をする前の道のり

就活する前と就活している最中とで話を分ける。まずは就職する前について。
Web制作業界を志した理由を考える【whyがないと挫折する】
そもそもなぜWeb制作業界にしたか。
この問いを自分に向けなければならない。なぜなら、whyがないと長続きしないからだ。
ただ、「なぜ?」を考えるのに時間をかけすぎてもいけないので、ぼんやりとした理由でOKだ。
で、私の場合、カフェとパン屋巡りが趣味なんですが、いざお店に到着して休業日だったーーみたいな状況を解決したい。が動機だった笑。
お店は貴重な新規顧客を失っているし、お客さんは時間と労力を失っている。網羅的にお店の情報を掲載したWebサイトがあれば、この課題を解決できるのでは?と思い、Webサイト制作の道を選んだ。
それにお店のブランディングやWebマーケティングにも興味があったと思う。これはおそらく私にWordPressブログの経験があったからかもしれない。
自分が思い描いたターゲットに向けて記事を書き、読者から反応(ex.記事を読む、コメントをくれる、紹介した商品が売れる)があったときの喜びが大きかった。
Web制作スキルをどうやって身につけたか【独学+コミュニティ】
Web制作のスキルを身につける手段はいろいろある。
- 職業訓練校に通う
- 書籍やYouTubeで独学する
- 民間のWeb制作スクールに通う
などなど。向き不向きがあるので一概にこれ!とは言えないが、私は独学、+αでコミュニティに所属を選びました。
学習の経過について
- 〜3ヶ月:書籍でHTML・CSSの基礎を学習
- 〜6ヶ月:Codejump(旧codestep)でサイト模写
- 〜9ヶ月:書籍でJavaScript・WordPress・PHPを学習
- 〜10ヶ月:UdemyでWordPressを補強
- 〜11ヶ月:コミュニティ(デイトラ)に所属し、刺激をもらう
- 〜12ヶ月:ポートフォリオサイトを作る(静的)
- 〜15ヶ月:WordPress自作テーマを作る
- 〜17ヶ月:現役のコーダーに模写サイトを添削してもらう(※有料)
- 〜18ヶ月:ポートフォリオを改修してWP化する
ざっとこんな感じで進めた。
独学で詰まった部分をネットの有料教材で補強したり、モチベーション維持のためにWeb制作のコミュニティに入ったりして、長く効果的な学習が続けられるようにした。
以下にレベル別にやってよかった教材を紹介する。
(※実際に自分が購入して何周もやり込んだ本や教材だけをご紹介するのでご安心を)
初心者向けの教材
「これから勉強をします」という方向けの教材から。
最初は一番カンタンそうな本からスタートした。いきなり難しいのに手を出すと挫折するのでオススメしない。
また、個人的には最初はマンガでもいいと思っている。全体像の把握が肝心だ。
中級者向けの教材
次は一通り学習を終えて、基礎が身についた方向けの教材。
- 作って学ぶHTML&CSSモダンコーディング
- プロのコーディングが身につくHTML/CSSスキルアップレッスン
- HTML+CSSコーディングの強化書
- スラスラわかるJavaScript 新版
- WordPress標準デザイン講座 20LESSONS
- WordPressオリジナルテーマ制作入門
- デジタル庁デザインシステム
- デイトラWeb制作コース
なお、デイトラWeb制作コースの紹介コードを差し上げますので、よろしければどうぞ。5,000円引きになる。
紹介コード:EPTNQ2RC
僕が躓いたのはWordPressだ。静的なサイトをCMS化するのはなかなか大変だった。一気に難易度があがったなという印象だ。なので、いろんな参考書を手に取ってさまざまな角度から解説を読み込んだ。
また、現役のコーダーさんがSNSなどでたまにセミナーを開催しているので、そちらにも積極的に参加していた。お世話になったのは下記の方々です。
セミナーは不定期に開催されるので、ぜひフォローして投稿をチェックしてみるといい。
また、よしおさんはオフラインイベントをよく開催しているので、ぜひ実際に参加してみてほしい。同じ志を持った人に会うことでモチベーションに火がついたり、軌道修正したりすることができるかもしれない。私も何回かオフラインイベントに参加させていただき、たくさんの刺激をいただくことができた。
実案件レベルのコーディングスキルを学べる教材
個人的によかったのはしょーごさん(@samuraibrass)が提供するコーディング添削だ。独学で身につけたスキルが実務レベルで通用するのかを確かめられる、いい訓練になった。
また、教材の内容はそのまま自分のポートフォリオに掲載が可能なところもGood。実案件レベルの高度なサイトなので、就職活動時にもアピールすることができる。
教材の種類は主に3つあります。
松・竹・梅のようになっておりまして、個人的には「松」か「梅」がオススメ。基本からじっくり学びたいなら「梅」で、サクッとしかし基本も学びたいなら「松」がいい。
詳しくは、しょーごさんのブログ記事「デザインカンプからのコーディング練習課題【オリジナルポートフォリオを準備できるようになりました】」をご覧くださいませ。
就活開始時のスキル【HTML〜WPまで】
就活開始時のスキルは下記のとおり。
- HTML / CSS / JavaScript(jQuery) / WordPress / PHP
- サイト模写:15個くらい
- デザインカンプからのコーディング:6個
- ポートフォリオ作成
- WordPress自作テーマ作成
- WordPressブログ歴2年半
今となってはやりすぎたかな…と思うけど、就活開始時はまだまだ足りないと思っていた。
なぜかというと、私の場合は年齢がいっていた(33歳)ので「未経験でも自発的に学習していてそこそこできる人」でないと厳しいと考えていたからだ。なので、学習にはガッツリと時間をかけてスキルを磨いた。
※たとえば「20代で独身、初めての転職」のような方はスキルが未熟でもポテンシャルがあるので採用に至るかもだ。
学習から内定獲得までの期間【長期で考えておく】
育児と家事をしながら就職活動を行う場合、最低でも1年くらいの期間は見込んでいたほうが良いと思う。僕は最初は子どもを家で見ながら学習していたため、ガッツリ学習に集中することができなかった。その結果、学習から内定までに約2年の月日を要した。
しかし、最初から「最低でも1年はかかるな。2年は我慢」と長期で考えいたため1年を経った後も焦りはなかった。SNSやネットでは「半年で内定!」のように短期間で目標をクリアしている人がいるが、無視していい。あなたとは状況がまったく違いますので。
ご自分のペースで淡々と課題をこなしていけばいいと思う。
【余談】SNSをやっていて良かった話
私は学習のスタートと当時に学習の記録をX(旧Twitter。以下、Twitter)で発信し始めた。
インスタでもYouTubeでもなくTikTokでもなく、Twitterを選んだ理由は発信するのが楽だったからだ。細かい話はともかく、各SNSの特徴を挙げると
- Twitter:140文字で投稿
- Instagram:10枚の画像で投稿
- TikTok:1本のショート動画で投稿
- YouTube:1本の動画で投稿
このようになる。「できるだけ学習に時間を割きたい。」と考えていた私にとってベストだったのがTwitterだった。Twitterが気軽に学習した成果を発信できる最良の手段だったのだ。
発信内容は「学習の記録+個人的な考え」にした理由
ただし。
「今日のご飯は〇〇」「育児疲れた」「イライラする〜」など、独りよがりの発信はNGだ。そこで私が強く意識したのは
- 学習の記録を、継続的に投稿
- 学習の過程で身につけた、お役立ち情報をシェア
- たまに、日々考えていることを発信
である。
学習の記録を継続的に投稿することで、「この人は長期に渡って自発的に努力できる人」だと証明できる。
また、お役立ち情報をシェアすることで同じ志を持つ人とつながることができるかもしれない。実際に私はつながることができた。
自分の考えも発信する
そして、重要なのが「たまに、日々考えていることを発信すること」だ。どういうことか。
それはあなたの人間性を知ってもらうためだ。あなたの本音を知ってもらうためだ。あなたの人生哲学を知ってもらうためだ。
あなたの人間性は、職務経歴書や履歴書、ポートフォリオサイトだけでは表現できない。いや、まったく表現できない。スキルや経歴の証明はできるけれど、人間性の証明はできない。だからこそ、SNSであなたの人生観や思想をつぶやくことに意味がある。
ですが。
「たまに」がポイントだ。
さすがに毎日自分の思いをつぶやいていると、「ポエムばっかりつぶやいてる痛い人」「自己主張が強い人」と思われてしまうからだ笑
本末転倒だろう。なので、ベースは学習の記録とお役立ち情報の発信にして、週に2〜3回くらい本音を織り交ぜる。このような戦略を僕は取った。
たぶん採用担当者はSNSの発信を見ている
「そういっても企業はSNS見ているんですか」こういう疑問も湧いてくるだろう。
私の推測(ほぼ確信)ですが、採用担当者は就活生のSNSを見ている。そして根拠もある。
私のポートフォリオには「監視カメラ(※MicrosoftのClarityというソフトで誰でも無料で設置できます。)」をつけているのだが、それを見るとTwitterをクリックする人が多かったのだ。
わざわざポートフォリオを見に来る人とは・・・たぶん採用担当者くらいだろう。
ポートフォリオではわからないあなたの素を、採用担当者は知りたがっている。
いざ就職活動スタート!

ここからは後半戦だ(この時点で私は1年半かかっていますので、ほぼ終盤だ。)
履歴書・職務経歴書をどうやって作ったか【厚労省のフォーマット】
※2023年12月26日現在、執筆中です
ポートフォリオサイトについて【必須】
ポートフォリオサイトについてはエントリー画面上は「任意」となっている場合が多いが、事実上必須だ。フロントエンドエンジニアを志すのであればスキルを証明する最良の手段になるためである。なので、まだポートフォリオサイトを作っていない方は作ろう。
ポートフォリオは「オリジナル」がいいと思う
「ポートフォリオサイトってなんでもいいの?」という疑問に思ったかもしれない。
ポートフォリオの種類として、
- ①ノーコードのテンプレで制作
- ②テンプレデザインをコーディングして制作
- ③デザインからオリジナルで制作(←オススメ)
大きく上の3つがあるが、圧倒的オススメは③だ。つまり、デザインも含めて完全にオリジナルで作ったポートフォリオだ。
理由は「差別化」だ。
もしもあなたがWeb制作会社の人事担当だったらと、想像してみてほしい。人事担当者なら日々いくつものポートフォリオを目にしているはずです。ひとつひとつ丁寧に見るべきですが、現実的にムリでしょう。もしテンプレ化されたポートフォリオが送られてきたとしたら「あ、このポートフォリオ、見たことあるな…いいや」と感じるはず。
だからこそ、デザインから自分で制作するべきだと思う。
とはいえ、デザインを完全にオリジナルで考案することは難しいと思うので、書籍やすでに内定をもらった人のポートフォリオを参考にしていい。オリジナルがいいと言っても基本となる「型」はあるので、骨格は真似してもOKだ。
ポートフォリオサイトはWP化しよう
続いての疑問は、ポートフォリオをWordPressに落とし込むか否か。見出しにもあるとおりですが、WordPress化まで完了しておくといいと思う。「WP化ができている=WordPressのスキルがある」ことの証明になるからだ。
また、私自身、面接時に「ポートフォリオはWordPress化していますか?」とよく聞かれた。また、面接では画面越しにポートフォリオのコードを説明する場面もあった(かなり焦った)。
私の観測範囲では、WordPressはフロントエンドエンジニアの応募必須条件になっているケースが9割だったで、やはりWordPressまでしっかり勉強しておく必要があるなと感じる。
企業をどうやって探したか【専門サイトとアプリを活用】
企業探しに時間をかけたくなかったので、私が取った戦略は「Web系の企業だけを扱うサイトやアプリを使って検索」だった。
そこで私が使っていたサイトは下記の4つだ。
- Green
- Web幹事
- 転職会議
- ライトハウス
上記4つはWeb系の会社しか扱っていない。なのでいちいちカテゴリを絞る必要がなく、検索の手間がグッと減るのがgood。
求人アプリ「Green」について注意点がある。
- フロントエンドエンジニアよりバックエンドエンジニア求人が多い
- 都市部の求人が多く、地方の求人は少ない
- 経験者の求人がメイン
扱っている求人に「偏り」があると感じたので、もしかしたら希望の求人が見つかりづらいと感じるかもしれない。
とはいえ、日々新しい求人が出てくる。
また、「Greenではバックエンドエンジニアの求人しか出していないが、企業HPではフロントエンドエンジニアの求人がある」なんてケースもあった。こういうケースも少なくないので、定期的にGreenもチェックしておくことを推奨しておく。
「地域名+Web制作会社」で検索するのもオススメ
この他にやっていたのは「地域名 + Web制作会社」でGoogle検索する方法だ。この方法では上記3つの方法で抜け落ちてしまった会社をすくい取ることができる上に、希望の場所(=地域)で条件を絞ることができるのでオススメできる。
意外と自分の身近な場所にもWeb制作会社があったりするものだ。
企業のリストアップについて
次は「どうやって企業を選ぶか?」が疑問かと思う。
業界未経験者は、選択権があまりない
その前に前提として、アラサー業界未経験からの就職の場合、選択権はあまりない。
- 実務経験がない
- スキルの証明が難しい
- 年齢的に中年に差し掛かっている
といったように、企業サイドからすればかなり不安なはずだ。なので、そもそも論として「自分勝手なことは言ってられないな」と思っておいたほうがいいだろう。
しかし、だからといってすべて企業の言いなりになればいいというわけではなく、譲れないポイントは明確にしておくべき。さらに、譲れないポイントを決めるためには自分が望むライフスタイルをイメージするといいです。
自分のライフスタイルを可視化する方法【1日のタイムスケジュールを書く】
じゃあ理想の生活を可視化するにはどうするか?僕がよくやっているのが、1日のタイムスケジュールを紙に書き出す方法だ。
- 朝何時に起きて、
- 何時にどんなご飯を食べて、
- どんな服を着て、
- 何時にお風呂に入って、
- 何時に寝るか
徹底的に具体に落とし込む。
パソコンで作ってもいいが、紙とペンで作るのがオススメだ。やはり自分の手を使って字を書くと定着力が違いますので。ぜひ、紙とペンを持ってカフェに行ってみてほしい。
ライフスタイルから逆算して企業を選ぶ
多くの人は、働き方にあわせてライフスタイルをあわせる。まだ自分の人生観が定まっていない20代のうちはいいかもしれないけど、30代になり家庭を持った方はNGかと。
すでにご家庭がある方が働き方に生活をあわせると、生活リズムが崩れてしまい、最悪、家庭(ご自身も)の崩壊に繋がりかねない。なので、オススメは「ライフスタイルにあわせて働き方をあわせる方法」だ。
目標と目的を分ける
目標と目的の違いは下記のとおり。
- 目標:Why(なぜ)
- 目的:How much(どれくらい)
目標は常に目的の上にあって、下にはない。そして、目標は数字で測ることが難しい。
しかし、よくある話だが、目標と目的がごちゃごちゃになってしまいがちだ。
たとえば、「月収30万円欲しい!」のは目標ではなく目的だ。なぜ、月収30万円なのか説明できなくてはならない。
しかし、得てして目標と目的がわからなくなってしまい、月収30万円が目標のようになってしまう。すると、数字に追われて意義を見失う。
だからこそ「自分の目標は何なのか」をはっきりとさせるべきだ。
私が重視したポイント
私の場合は「家族や地域との時間を大切にしつつも、一方で、余った自分の時間を社会に還元したい。それは私という人間を育ててくれた社会への恩返しになる。」と考えていた。
そして、この目標を叶えるために、下記の点を重視した。
- 企業理念に共感できるか(長く、自発的に働きたいから)※最重要
- 業務内容にコーディングがあるか(コーディングスキルを積みたいから)
- WebデザインやUI・UX、Webマーケティングもあるか(将来的にコーディング以外の分野もやりたいから)
- 年間休日120日以上(家族や趣味の時間を確保したいから)
- みなし残業が多すぎないか(許容できる残業時間を決めておく)
反対に、「給料の額」や「福利厚生(退職金や社員住宅など)」にはあんまり重視しなかった(未経験にも関わらずお金や福利厚生にこだわるのは筋違いな気もする)
応募方法について【結論:直接応募】
応募方法については、ちょっとしたコツがある。
すべて企業のホームページから直接申し込みました
求人サイトやアプリから応募ではなく、転職・求人サービスで求人を見て、企業のHPから直接応募するという流れがオススメだ。
理由は次の2つ。
- ①未経験で応募する:求人を掲載するのに数十万〜数百万円のコストがかかっているため、未経験者を採用しにくい。
- ②自己アピールがしにくい:求人サイトからの応募はテンプレ化されており、自己アピールが不十分になる
なので、応募は採用募集ページがあればそこから、なければ問い合わせフォームから直接応募した。
採用募集ページがある場合だと応募条件(経験者のみ、フロントエンジニア歴◯年以上)などと書いてある。他には
- HTML/CSS/JavaScriptを使ったコーディングの実務経験1年以上
- WordPressの実装経験
- Web制作会社、あるいは類似企業の勤務経験2年以上
- Webサイト制作経験者
このような条件だ。
しかし、私は募集条件をそこまで気にせず応募した。
未経験者であってもある程度学習をした人と、まったくの学習ゼロ完全未経験者の人とでは意味が違う。
- 学習済み・実務未経験者:要項の意味が理解でき、架空サイトを作った実績がある
- 学習ゼロ・実務未経験者:そもそも要項の意味が理解できない
なので、募集要項に実務要件があったとしても相応のスキルが身についていると仮定して応募した。
応募文はテンプレを作っておくといい
応募のコツとして、応募文のテンプレートを作っておくと効率がアップする。
- 自己紹介
- 志望動機(※ここだけ企業ごとに変える)
- 自己PR
- スキル・扱える言語
- 学習過程
- ポートフォリオサイト添付
- 職務経歴書・履歴書添付
私がテンプレート化していたのは大体上記だ。
就職活動の状況はスプレッドシートで管理
「数社エントリーして即内定!」のような一部の天才を除き、未経験からの就職の場合、最低でも20社(30〜50社は当たり前)は応募することになる。
そこで重要になるのが「応募状況の管理」だ。
私はスマホでもPCでも閲覧したかったのでスプレッドシートで管理していた。が、フォーマットはお好きなものでいいと思う。
私は次の項目を作っていた。
- 会社名
- 会社ホームページURL
- 会社SNSのリンク
- 第一印象を言葉に
- 応募した日
- 合格・不合格の通知がきた日
- 面接日
人によってはもっと細かく管理している方もいると思うが、ざっくりと全体像を把握するためだったので上記のようにした。
※もしこの記事を読んで参考にしたい方がいらっしゃればシートを差し上げますので、TwitterにDMください。
面接について
面接の準備は、書類選考が通った後から始めた。
自分の言葉でしゃべれ
常識とは違うかもしれないが…個人的に思う面接対策はFAQリストをまとめておく程度でいいかなと。
もしも面接で着飾って内定をいただけたとしても、実際に仕事をしてみたらすれ違ってしまった…みたいな状況になってしまいかねないからである。
面接は恋愛と一緒だと考えていて、付き合う前にカッコいいカワイイ部分だけしか知らない状態だと、カッコ悪い部分を見たときのショックは大きく、受け入れられないかもしれない。
だからこそ、多少つっかえてもいいから自分の言葉でしゃべる。自分のペースでそのとき聞かれた質問に対してそのときの自分の考えを述べる。これでいいのかなと、私は考えているし、それでよかったと思った。
とはいえ、まったく準備しないのも相手にとって失礼(相手の時間をいたずらに奪いかねない)なので、事前に想定質問は考えておくといいとは思う。
面接の方法について【オンライン・オフライン両方】
面接の方法はオンライン・オフライン両方ともありました。アラサー世代の私にとって、オンライン会議の経験はありました(コロナ禍)が、採用面接でのオンライン面談は経験がなく、不安だった。
私の拙い経験で恐縮ですが、オンライン面接で必須なのは
- パソコン(資料を見ながら面接できる)
- イヤホン(相手と自分の声がよく聞こえる)
だ。
服装については指定はなかったが、誠実さが伝わるようにシャツとジャケットを着た。正解はわかりませんが、「精一杯の思慮が伝われる形がいい」と思う。Tシャツやパーカーはオススメしない。
あとは、相手への配慮として、カメラの背後に余計なモノが映り込まないように壁を後ろ向きにしたり、エアコンやテレビを切っておくのも効果的かなと思った。
実際に聞かれたこと【表にまとめました】
- 自己紹介
- 職歴・略歴
- 志望動機
- 前職の仕事内容
- 希望年収
- 強み・弱み
- JavaScriptでできること
- 長い期間続けていること(趣味でもいい)
- 3年後・5年後のキャリアプラン
- ポートフォリオで工夫したこと
- ポートフォリオの中で一番自信がある作品
- 言語の中で一番得意な言語は
- ポートフォリオサイトの制作にかかった時間
- どうやってWeb制作を学習したのか
- 学習期間はどれくらいか
- Web制作業界に転職しようと思ったきっかけ
- よく使用するアプリやWebサイト
- 今後、どの分野を極めていきたいか
- 今勉強してるものはないか
- 仕事で最も大事にしていることは何か
- フロントエンドエンジニア以外には興味がないか
- 今後、コーダーの役割はどうなっていくと思うか
- どんなときに仕事にやりがいを感じるか
- 仕事に求めるものは何か
- 子どもは何歳か
- 子どもは保育園(幼稚園)に通っているか
- 前職でマネージャー経験(管理職)はないか
- 前職を退職した理由
- 安定を捨てる(公務員を辞める)のは怖くなかったか
- 前職で問題にぶつかったときにどうやって乗り越えたか
- 選考状況は
- Sassはできるか
- GitHubはできるか
- 弊社の理念は
- 弊社の事業内容は
最後に【人と比べるな。】

私は学習開始から内定まで約2年の歳月がかかりました。相場はわからないが、個人的な感想としては「長かったな」といった感想だ。
- どれくらいスキルがあればいいのか不明
- 実務未経験だけど本当に内定がもらえるのだろうか
- キャリアに穴があいてしまったけど大丈夫なのかな
こういった不安と常に隣り合わせの日々だった…
SNS上で「学習開始から半年で内定をもらった!」「3ヶ月で案件獲得!」など、なんだか凄そうな人ばかりだ。
実際に私もこういう投稿を見ると余計に不安になり、焦ってしまい、最悪「俺ってだめ人間なのか」と落ち込んでしまい学習がストップしてしまうこともありました。
しかし、ネット上の「凄い」人とあなたは単純比較ができない。住んでいる場所や同居人の有無、子どもの有無、もともとの能力やセンス、使える時間的・体力的・金銭的リソース、年齢、性別、学歴、経歴などなどなどなど。
ありとあらゆる条件が異なりますよね。背景がまったく違う。人と犬を比べるようなもので馬鹿げている(犬に失礼)。
だから、これらの前提条件の違いをすっ飛ばして単純比較し、落ち込む必要はない。あなたはあなたの持っているリソースを最大限使って日々全力で過ごすのみだ!
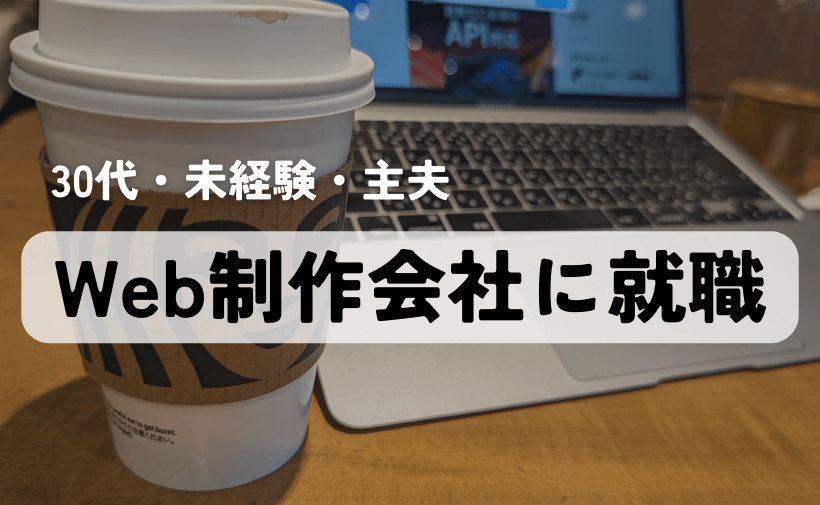
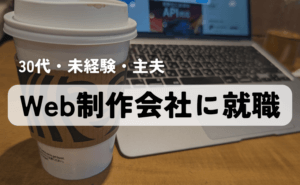
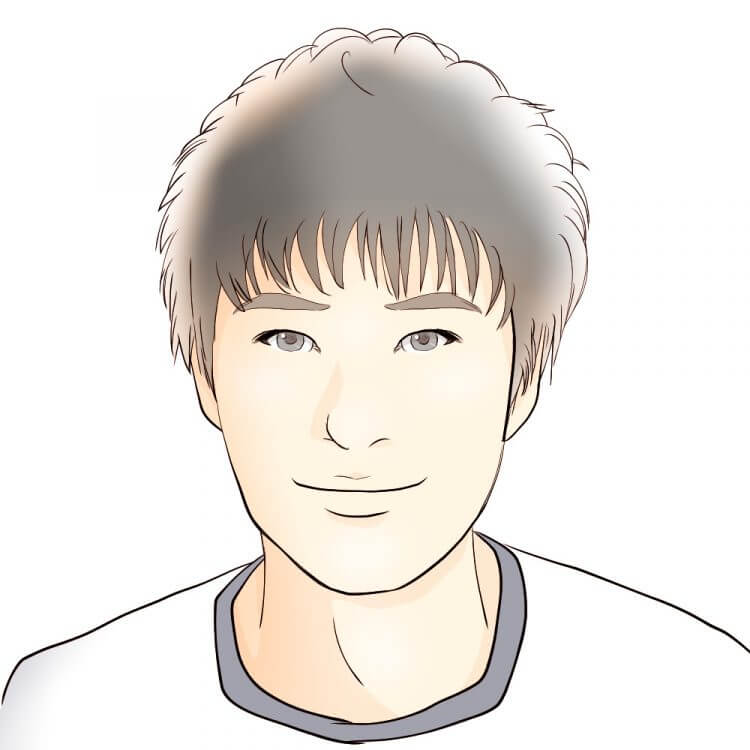
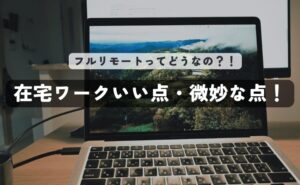

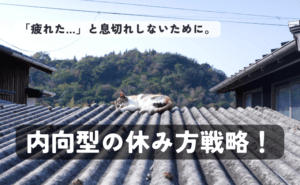
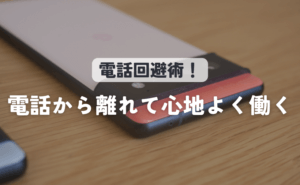

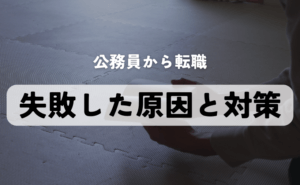

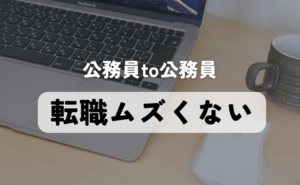
コメント