- 将来的には子どもが欲しい
- 子育てに適した間取りって?
- 賃貸か持ち家かで悩んでいる
こんな方に向けて。
この記事を書く僕は妻と3歳の息子と3人暮らし。2023年7月末、2LDKから1LDKの賃貸マンションに引っ越した。
元の住居は2LDK、新居は1LDK。あえて狭い家への転居になる。
狭い家に引っ越した理由は、
- 使っていない部屋があった:50%
- 使っていないモノがあった:30%
- 気分転換:20%
主にこの3つです。
常識的には家族持ちは「広い家に住んだ方がいい」はずで、欲を言えば「持ち家がいい」かもですが、本当かな?と私は思っています。

狭い家に引っ越した理由
冒頭の繰り返しですが、下記。
- 使っていない部屋があった:50%
- 使っていないモノがあった:30%
- 気分転換:20%
理由その1:使っていない部屋があった

最大の理由が未使用の部屋があったことだ。
2LDKの間取りだと
- キッチン
- リビング・ダイニング
- 部屋①
- 部屋②
我が家の実態は下記だった。
- キッチン
- リビング・ダイニング
- 部屋①:寝室
- 部屋②:物置化
2部屋あるうちの1部屋は寝室として毎晩利用していたが、もう1部屋はほぼ未使用。かつては物置部屋と化し、ダンボールの山ができていた。
思春期までは子ども部屋は不要説
そうはいっても「余っている部屋は将来子ども部屋にできるのは?」と思ったかもしれない。僕もそのように考えた。
しかし、子どもが自分の部屋を持つようになるのは小学校の高学年になってからのはず。
実際、私も妻も自分の部屋が与えられたのは小学5年生になったときだ。
また、子どもの遊び場(プレイルーム)にすることも検討したが、結局はおもちゃをリビングに持ってきてリビングで遊ぶので意味なしと判断した。
子ども専用の部屋は思春期までは不要!と結論づけた。
家にいるのは夕方〜朝だけ
さらに共働きの我が家では平日の日中は家にいない。
我が家の日中のスケジュールを下記のように予測した。
- 6:00 :起床&身支度
- 7:30 :家を出る
- 9〜17 :仕事
- 18:00:帰宅&夕食
- 23:00:就寝
家に滞在する時間は夜18〜翌朝7時半だ。
つまり、1日の半分を家の外で過ごし、家の中で食事と睡眠に時間を使う。
子どもが幼稚園や保育園に通っているなら、子どもも同じく家にいない。
つまり、親も子どももほぼ家にいないことが判明した。ほぼ外出しているのに広い家は不要では?と考えるようになった。
理由その2:使っていないモノがあった

我が家には、押入れやクローゼットに使っていないモノがたくさんあった。
たとえば
- スキー用ウェア
- 趣味の釣り用具
- サイズアウトした服
- 読み終わった本(再読しない)
- 結婚式でもらった引き出物 etc…
こういったモノは大抵、押入れの奥にしまってあり、その存在すらも忘れてしまうし実際そうなっていた。
でね。ある日、ふと思った。
「使わないモノに占拠された生活ってどうなん?」と。
使うモノならともかく、使わないモノのためにその収納場所を確保している事実だ。懐にも負担がかかるし、何よりモノに対しても申し訳ない気持ちが込み上げてきた。
だったら、「これを必要としている人に譲るか、一層処分しよう」と考えた。まぁ断捨離だ。
でも、断捨離にも限界がくる。やっぱり物理的に空間があるっていうのはデカくて、収納できてしまうから見えない。実態が霞んでしまう。
ゆえに、いくら処分しても減らない。押し入れは、クローゼットはパンパンのまま。
そこでたどり着いた結論は、狭い家への引っ越しでだった。
収納できる空間自体をなくせば、嫌でも収納から溢れるモノが出てくる。事実に目を背けることができなくなり、行動が促される。
その結果、荷造りの段階で大量の不要品が発掘され、一気に断捨離することができた。
理由その3:気分転換

人が変わる方法は、大きく3つの要因があると考えられる。それが
- 時間配分を変える
- 付き合う人を変える
- 住む場所を変える
この3つ。このうちどれか1つでも変えると強制的に変わることができるらしい。
前に住んでいたところには6年半住んだので、正直飽きていた。倦怠期というか、いまいちテンションがあがらない。妻もそう感じていたようで、そろそろ別の場所へと考えていたようだ。
そこで、妻と相談し、新居へ引っ越すことにした。
引っ越すときの注意点
ただし。
僕は「平凡な日常と地域への貢献こそ究極の幸せ」だと思っているので、縁もゆかりもない場所に引っ越すのは反対だしオススメできない。日常がぶっ壊れ、地域とのつながりがなくなってしまうからだ。
また、子育てをしているなら、実家(もしくは義実家)とも物理的な距離は重要だ。
僕の感覚で言えば、実家(義実家)から車で30分圏内に住むと子育てが劇的に難易度が下がる。距離にして10kmくらいだ。
難しい場合は兄弟姉妹との距離でもいいと思う。
自分たちだけで子育てしない工夫を。
子育ては総力戦だ。団体戦といってもいいかもしれない。ぜったいに個人戦ではない。
だから、子育てを自分ひとりで解決しようとしちゃダメだし、できない。いずれ限界がきく。すぐくる。
あと夫婦2人だけで解決するのもダメ。これも限界がくる。片方が倒れたらお仕舞いだ。
そもそも人間は群れで生きてきた動物なので、核家族で子育てをすること自体が不慣れだ。率直に言って向いてない。
だからこそ、お互いの両親や兄弟姉妹さんの力を借りよう。遠慮なく借りよう。全然恥ずかしいことではないだ。ふつーのことだ。
両親は孫の世話=過去の追体験になるので、きっと喜ぶはずだ。兄弟姉妹は将来の子育てを今体験できるので、きっと喜ぶはずだ。
お金に依存した子育てから脱却
ただ、実家を離れて自立もカッコいいよね。共働きで、子どもは保育園に入れて、仕事も家事も妥協なく両立して。そんな家庭を築く夫婦は理想だ。僕もそうなりたい。
でも、現実問題として仕事と育児の両立は思っている以上に負担が重い。リスクが高い。難易度が高い。大量のお金が必要になる。
行政(公共サービス)に頼むにせよ、民間(ベビーシッター)に頼むにせよ、大量のお金が必要だ。大量のお金が必要になるということは、その分大量の労働が必要になる。大量の労働が必要になるということは、働くための時間が必要になる。
「家族以外の第三者に子育てを委託する」ということは、つまりお金がモノをいう世界だ。実はかなり難しいことをしているし、リスキーだと思う。
だから、実家との物理的な距離は近くしたほうがいいんじゃない?と、私は考えている。
「持ち家」ではなく「賃貸」に住むワケ

ここからは後半。
そもそも、全体の傾向として結婚して子どもが産まれるタイミングで家を買う人が多い。
僕の周りでも子どもの出産を機に一軒家ないしマンションを購入した友人は多い(というか大半)
しかし、家を買う明確な理由があるならともかく、「なんとなく常識だから〜」と家を買うのはどうかな?と私は思う。
住宅ローンは身の丈に合わない
家を買う人の多くが組む住宅ローン。要するに借金だ。住宅ローンとかいう言葉だと紛れるが、借金に過ぎない。
この記事を書く2024年現在は首都圏の建物価格が上昇していて、東京だと平均取得価格が1億円近い。埼玉、神奈川、千葉でも6〜8000万円近くする。
控えめに見積もって仮に「6,000万円」の家を以下の条件で買ったとしたら…
- 頭金:1,000万円
- 住宅ローン:5,000万円
- 金利:0.3%
- 期間:35年
月々の返済額は125,421円、支払利息総額は2,676,967円となり、30歳の人なら65歳まで、35歳なら70歳、40歳なら75歳まで、だ。※出典:@ローン計算
厳しくないですか、、、?
35年間、毎月12.5万円を返済することはできるか?!を考えたとき、「難しいだろう」というのが私の考えだ。
ただし、経済状況は家庭よってちがうので、「5000万のローンならへっちゃら!」という人もいるはず。そういう方は思い切って家を買えばいい。
私が言いたいのは、「一般論や社会の雰囲気に左右されずに、個別に検討するのが重要だ!」ということだ。世間を気にしすぎて、自分を見失っては本末転倒だ。
ちょっと脱線した。話を戻す。
「フラット35を使えば低金利で借りられるし、税金の控除を受けられるからお金の不安は解決できる!」と思うかもしれない。
たしかに、節税のメリットはある。また、政府は「少子化対策」と称して、フラット35にもテコ入れしようとしている。
子育て世帯等が良質な住宅を取得する際の金利負担を軽減するため、住宅金融支援機構が提供する長期固定金利の住宅ローン(フラット 35)の金利優遇について、ポイント制を活用し、住宅の広さを必要とする多子世帯に特に配慮しつつ、2024 年度までのできるだけ早い時期に支援を大幅に充実させる。
出典:内閣官房
子育て世代にとっては嬉しいニュースだ。
が、持ち家にかかるお金は購入時だけではありません。
たとえば、一軒家だと
- 火災保険
- 地震保険
- 家財保険
- シロアリ駆除
- 屋根補修
- 壁紙張替え
- 水回りリフォーム etc…
ざっと思いつくだけでもこんなにある。
問題は不動産業者も銀行マンも、そして、家を買う本人も家を買った後の費用を考慮にいれない点だ。
不動産屋は「賃料で家が買える」と言い、銀行マンは「低金利で貸せる」と言います。決して維持費には触れない(新車販売も同じ)
なぜか。維持費もいれると賃貸よりも高いからだ。誰も家を買ってくれなくなるからだ。
消費者である僕たちは賢くなる必要がある。不動産屋や銀行マンが言わないことに注目したい。
子どもが巣立ったら大きい家はいらない
「子どもがいるから大きい家が欲しい!」と思うのも理解できる。我が家にも3歳の子どもがいるので、その気持ちは痛いほどわかる。
家中ところ構わず走り回るし、ギャーギャー騒ぐしで、隣人が迷惑していないか不安になる…
しかし、だからといって「家を買う」選択肢は我が家にはない。
大きい家が必要な期間はせいぜい15年と短いからだ。子ども部屋が必要になるのは中学生くらいからで、だいたい13〜15歳。
で、子どもが家を出るのは社会人になってからだとすると、子どもは25、6歳です。兄弟姉妹がいる場合は+5年くらい?
この期間のためだけに高リスクの借金をしてまで家を買うのか?と考えた結果、「賃貸でもいい」という結論になった。
なお、子どもの騒音トラブルに関しては「木造住宅に住まない」でほぼ解決できる。
理想は鉄筋コンクリート造だが、軽量鉄骨でも遮音性は高い。それでも気になる方は戸建て賃貸や1階に住めばOKだ。
いずれ不動産価格は落ちる
じゃあ「夢のマイホームは諦めたのか」
いいえ、諦めていない。実は子どもが巣立った後にマイホームを購入しようと考えている。理由の1つには、日本の不動産価格は下がるのでは?と睨んでいる。
今は2024年。子どもが成人するのは2040年。日本の人口動態予測はというと
- 2023年:1億2454万人(8月1日時点)
- 2025年:1億2300万人
- 2030年:1億2000万人
- 2035年:1億1600万人
- 2040年:1億1200万人
- 出典:国立社会保障・人口問題研究所
つまり、子どもが巣立つ頃の2040年は、今よりも1200万人も人口が減少する。
1200万人はほぼ東京の人口(東京の人口は1400万人)と等しいので、ものすごいインパクトだ。今日から16年かけて東京の人口が日本から消える。控えめに言って、ヤバい。
つまり、人がものすごい勢いで減っていく未来がほぼ確している。
というとは、、、不動産価格も落ちるはずだ。
不動産価格が暴騰している今、無理して家を買う必要はないのでは?と考えるのはこういった背景がある。
マイホームは、子育てが終わったタイミング
それともう一つ。
マイホーム購入にあたって「人が増えること」を想定されるが、「人が減ること」は想定されない。
だから、家は最大居住人数に合わせたサイズになりがちだ。しかし、家族全員で暮らす日々は人生全体でみたら一瞬だ。子どもは旅立つし、パートナーも旅立つ。もちろん、自分も旅立つ。
余談だが、僕は仕事柄、広い家に1人で暮らす高齢者をたくさん見てきた。僕はもともと区役所でケースワーカーをしていた時期があった。
老後をたった1人で、しかも広い家で暮らす不便さ。経済的な負担。管理の難しさ。
こういう人をたくさん目撃してきた。
もちろん家には思い出が詰まっているから、一概にダメと決めつけることはできない。思い出はお金で買えないし、過ぎてしまった時間を取り戻すことはできない。だけど、買う前からやがて住む人数が減る未来が見えているのにそれをまったく考慮しないのはどうなんだろう。
と、僕は考えた。
最後に

引っ越してから8ヶ月が経った。徐々に家の中が整い、また、いつもの平凡な日常が戻りつつある。
今回の引っ越しで抱いた感想は、
- 荷造りで大量の粗大ごみが出た
- 1LDKでもまったく問題なかった
- 子どもが産まれる前に引っ越せばよかった
- 搬出搬入はすべて業者に任せたほうがよかった
だ。
以前よりも狭くなり収納に関して不便さは否めない。
置けなくなった家具もあった。仕舞えなくなった収納ケースもあった。収納できない服もあった。
しかし、「適度な不便は、過剰な便利に勝る」とも思った。
不便があると「どうしたらいいか?」を頭を使って考えるようになる。また、手を動かすようになる。
すると「日々生きている」という実感を持つことでできるようになった。
これは望外の喜びであり、これからも大切にしていきたい感覚でもあった。
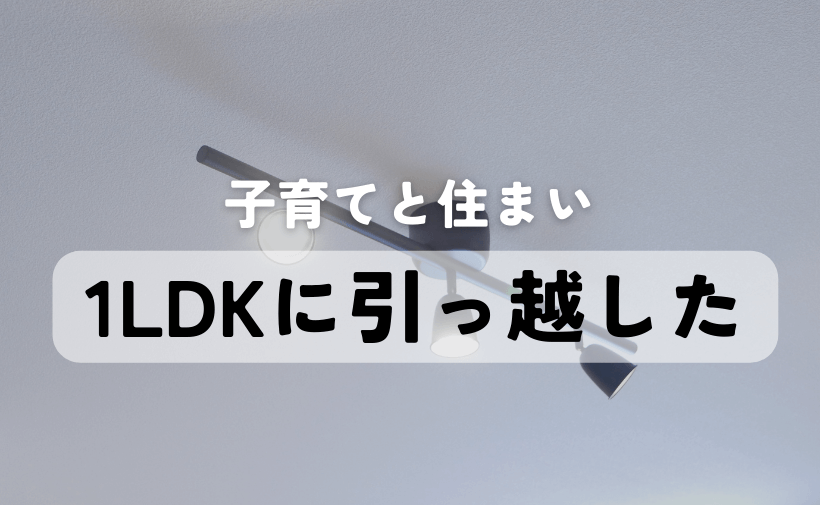
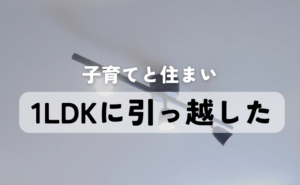
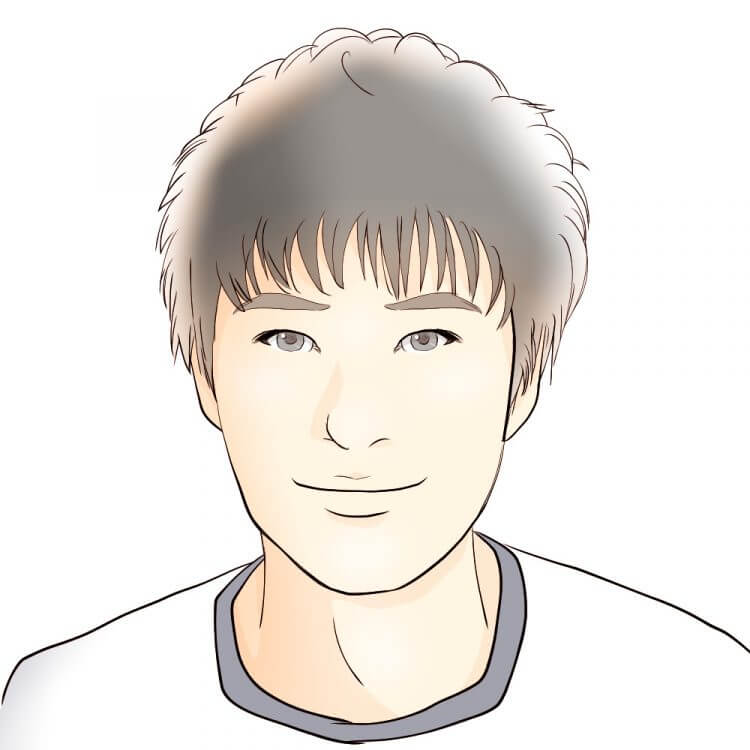

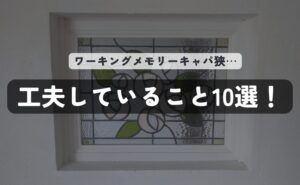

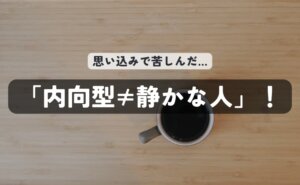

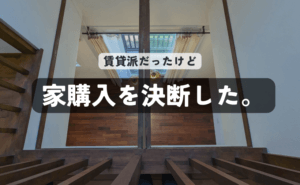
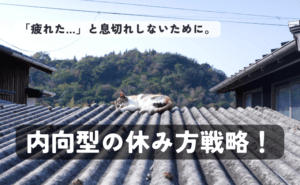
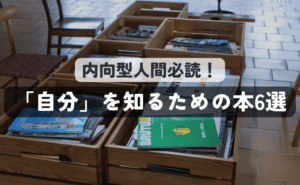
コメント